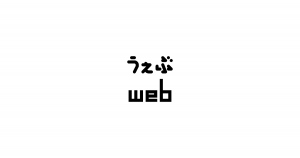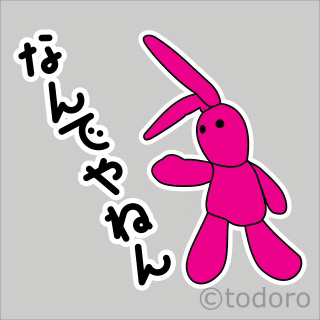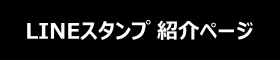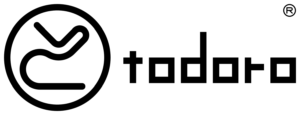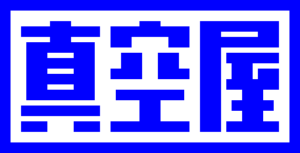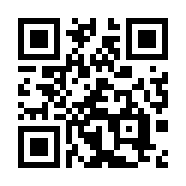町工場における営業職の役割と必要性
小企業、零細企業向けの記事です。
タイトルそのままですが、小規模な製造業のメーカーにおいて営業人員が担う役割と必要性について書いてみます。
ちなみにうちの会社は全社員で17名、営業部に4名(うち営業2名、営業事務2名)で、代表者である僕も担当としてゴリゴリ営業で動いている、という構成です。
営業という機能を専任ではなく例えば製造が兼務するようなことも可能と思いますが、下記に書いた物理的な制約も発生するので総合的に考える必要があります。
目次
町工場における営業の役割
役割としてはこんな感じじゃないでしょうか。
「製造現場と客先の円滑な橋渡しをする」ことで「製造行為の付加価値を上げる」です。
おそらくこれに尽きます。
現場が苦手なことってあります。
たとえば、経験上「資料を作る」「謝る」なんていうのはあまり現場とは相性が良くないです。
これは当たり前の話で、キャリアや環境や求められるスキルがそもそも異なるからです。
たとえば4年制大学の文系学部なんかにいくと、ゼミやらなんやらであまり仲良くもない相手に対して順序立てて話す機会なんかは多かったりします。
いきおいディベートというかディスカッションに慣れていきます。
また、物理的な側面も大きいです。
たとえば汎用旋盤なんか回していると、手は油まみれになります。
メモはおろか、電話も取りにくいです。
従事する作業によっても、かなり程度の差があります。
「2コール以内で電話が取れるか」「静かな環境で電話ができるか」なんていうのも物理的な制約です。
こういう製造担当の苦労というのは製造担当にしかわかりません。
自分も小学生の頃から現場に出入りして、入社2年目で数週間工場に寝泊まりして、どの職人よりも遥かに長時間労働していたけど、最後の核になる部分はわからないと思う。
自分は製造担当ではないから。
大ベテランの職人から「あんたに言うてもわからん」と言われたこともあります。
ほんまにその通りやと思う。
ただし別のことしてるから、別のいろんなことがわかる。
当たり前の話です。
経営者で職人やってはる人は、職人目線をもっているという部分は強いですね。
やから職人が素直に謝ったりできなくても、その裏の考えや想いを汲み取ることはできるし、そう努めないといけないな、と思いました。
「声になって出てこない」というのと「悪いと思ってない」は違うから。
全員がうまく自分の気持ちや考えを言葉にして外に出せるわけではないです。
そして大きい声で言ったもん勝ちみたいな世界は僕は好きではないです。
ほんまに悪いと思ってなかったら付き合い考えさせてもらいますけどね。笑
客先に直接謝罪せえと言ってるわけやなし、社内で「すみません」くらいあってもいいのにと思うことはあります。笑
町工場における営業の仕事
自社の例も交えて書いていきます。
営業の仕事といっても、分岐があります。
ひとつは対面的な仕事。
もうひとつは事務的な仕事です。
自社の例では、前者は営業が、後者は営業事務が担っています。
必要なスキルも違うし、かかるストレスも違うし、当然手当も違ってきます。
自社の例では営業は運転免許が必要ですが、営業事務は不要です。
前者は、直接お客さんと対面や電話やメールでやり取りをして、要求を聞き取って見積を提出したり、納品に行ったりするのがメインです。
特にお客さんの本音を聞き取る、というのは営業の醍醐味でもあります。
建前と本音が違うことは往々にしてあります。
ルールと実態が違うこともよくあります。
メールには書けないけど電話では話せることもあります。
あまり王道ではないですが、信頼があるから特別扱いというか目をつぶってもらえることだってあります。
特に新規取引先の獲得や加工ミスなど、特別なことやイレギュラーなことが起きた場合に、営業の機能が本領発揮されます。
本当に営業のうまい人は話し上手ではなくて聞き上手とかよく言いますよね。
自分もこんなことがありました。
25歳くらいの時ですかね、お客さんと話してて、1時間くらい相槌打ってただけで、最後「若いのにお詳しいですね」と言われたんです。笑
いやいやいや、なんにもゆうてへんがな。笑
それくらい、人は人の話を聞いてないし、自分の話を聞いて欲しいもんなんですよね。
営業としての会話中のコミュニケーションスキルは本当にたくさんあります。
待つ、顔を向ける、返事をする、手を止める、体を向ける、話す前に聞く、相槌を打つ、聞き返す、理解しようと努める、伝えようと努める、質問する、書いてまとめる、具体例を提示する、理解していることを示す、訊かれたことを覚える、わからないことを調べて後日回答する、ホンマに些細なことで良いコミュニケーションが取れるようになります。
「ライバルももっている能力」では差別化はできません。
たとえばGoogle検索やChatGPTは「みんなが使えるもの」です。
「本気で話を聞く」というようなスキルというか心がけというか行動は相手にかなり伝わります。
逆も然りです。
町工場では事務の仕事、いわゆるバックオフィス業務と言われる部分が割と過小評価されがちです。
というか事務系の仕事は割と「地位の低い仕事」と見なされがちです。
まあ、もったいない話です。笑
自社の例でも、自分が入社した2009年には営業事務という立ち位置の人員はいませんでした。
いわゆる「事務員さん」はいたのですが、「こういう機能をここで担う」みたいなものはなかったように思います。
今では営業が営業担当をもっていて、営業事務も営業担当をもっています。
つまりお客さん1社につき営業と営業担当が1名ずつ付いている、という状態です。
小さな組織では兼務が多いので、「やれる人がやる」というスタンスはある種重要で、自社もそこから抜け切れていないのですが、少なくともお客さんによって担当をきっちり分ける、というのはかなりうまく機能したと思います。
何よりも担当する人の当事者意識がすごく変わってきて、実際担当の仕事っぷりも変わったように思います。
大変な部分は当然あると思うけど、傍目には生き生きしているようにも見える。
おかげで全体を統括する自分の肩もだいぶ楽になりました。
そして営業事務がすごい仕事を捌いてくれます。笑
見積とか仕様の打合せも製造担当とやってくれて、見積を承認する時にはあまりコメントすることが無いほどです。笑
親バカであれですが、よその営業さんよりうちの営業事務の方が図面読めるんちゃうか、と思うことすらあります。笑
正直少なくとも大手の一般職とは比べ物にならないくらい給料も高いと思います。
たぶん。笑
ちなみに事務職というのは、工場の仕事としては求職者からも比較的人気が高いように感じます。
うちでは営業事務は2人とも女性で、1人は新卒入社で、もう1人も20代で大きい会社から移ってきてくれました。
上の方で書いた「製造現場と客先の円滑な橋渡しをする」というのは「直接顔を合わせて話す」ということだけではなく、ISO的に書くと客先の「要求事項」を製造に「インプット」して、顧客満足の高いサービスを「アウトプット」するということも含んでいます。
つまり「図面には書いてないけどお客さんが期待や要望していることは製造に盛り込む」ということです。
自社ではこの部分をかなりフォローしていて、顧客満足に繋げているつもりです。
たとえば「ここの面取りC5になってるけど、ちょっと丸めに取っといてほしいねん」とか「こっち側絶対溶接せんとってな」とかそういうことです。
はっきり言って、いくらでもあります。
お客さんは欲張りな生き物なので、掘れば掘るほどナンボでも出てきます。笑
さらに言えば「最初に聞いたときはうまく反映できた」ことでも、リピートになると抜けてしまうことがあります。
客先からすると「前回は、やってくれたのに」「前の方が良かった」「品質が下がった」という認識にすり替わってしまうことがあります。
それをうまく回避するのが上記のような行為です。
営業が掬い上げて、営業事務が製造に落とし込む、というような流れで進めています。
ここは自社の砦と心得て徹底的にやっています。
でないとうちみたいな小さな会社が宇宙、防衛、放射線なんていうややこしい分野の仕事をやらせてもらうのは難しいです。
営業は町工場に必要か
これは会社の方針や事業形態によって大きく異なる部分です。
小規模の製造業であれば専任の営業職は置かない、というところは結構多いです。
実際うまくいってそうな会社さんも多いです。
無理に置く必要はないと思っています。
じゃあどういう工場が営業を必要とするのかですが、これは「管理が必要な仕事を取りにいくことで付加価値や利益率を上げたいと思っているかどうか」だと思います。
逆に現場の力をゴリゴリ上げて「付加価値や利益率を上げる」という方法もあるわけですから。
プロセスの違い、という感じです。
わかりやすい例は検査書類ですね。
いわゆるややこしい仕事というのは書類が付きまといます。
小規模な町工場が従来苦手な部分のひとつです。
そして、ややこしい仕事というのは利益率が上がります。
僕らの規模のメーカーでも、それなりにやっかいな案件になってくると検査書類が100ページを超えます。
それだけの枚数の検査書類をまとめようと思うと、途中はかなり煩雑になります。
製造人員だけではなかなか難しいです。
溶接は15分で終わるけど書類をまとめたりするのがめんどくさい、というような仕事もあります。
現場は嫌がる仕事です。
現場が嫌がるということは他社も嫌がるので、これも利益率は良かったりします。
同様に、打合せや現物を見に伺ったり、仕様の擦り合わせのために資料をまとめたり、というのも製造人員が兼務してしまうと、その時間製造が止まるので対応が難しい部分です。
1つの案件で客先や協力工場とやり取りするメールが数百になることもよくあります。
結局「自社の強みを伸ばす方向性の延長線上はどうなってるか」に尽きると思います。
うちの会社では、真空チャンバーという少しややこしい製品を主力にしていることもありますが、この部分を引き続き伸ばしていこうとしています。
自社の相当マニアックな事例になりますが、「SUS316Lの板厚0.5mmの配管の溶接品で、耐圧試験(加圧)もヘリウムリークテスト(減圧)もPT(浸透探傷試験)もRT(放射線透過試験)も必要で、検査記録は溶接線毎に管理、ヘリウムリークテストはフード法・吹き付け法・スニファー法すべてが必要」なんていうのは、僕らが得意とする対応内容です。
ちなみにPTというのは薬剤を使った欠陥の検査方法、RTというのは人間のレントゲンと同じようにX線を使った欠陥の検査方法、溶接線というのは1つの溶接箇所という意味で、フード法・吹き付け法・スニファー法というのはそれぞれヘリウムを使って漏れが無いことを確認する手法の一種です。
上記の件、実際にあった仕事です。笑
営業代行はどうなのか
営業代行という形態がありますね。
今のところ、ですが、個人的な見解としては採用する予定はありません。
理由は3点です。
1. イメージが悪い
これは、しつこくて失礼な迷惑電話をかけてきたり、スパムメールを大量に送ったりしてくる業界全般に言えることですが、そういう企業や人たちのせいで業界全体のイメージが悪化したことに起因します。
おそらく真面目にやっている方もいるんでしょうが、電話やメールから「この人は良い人」みたいなものを選別するのは困難です。
「業界全体として過去どのような努力をしてきたかの蓄積」が問われる部分です。
かなりしつこい人が多い印象です。
しつこい、というか、人に迷惑をかけてでも自分の営業インセンティブを獲得したい、という印象ですね。
「あなたにメリットがあるから提案しているのに話を聞かないなんて、あなたは愚かだ」というスタンスの人も見かけます。笑
電話がかかってきた場合、電話を受けながら並行してその電話番号を検索してみるといいと思います。
ちなみに製造業でこういう執拗な営業活動をする会社はあまりないイメージを勝手にもっていますが、どうでしょうか。
2. 会社間の繋がりを無視してしまう。
こんなことがありました。
実際の体験談を2つ書きます。
1つめ。
電話のパターン。
ある日電話が鳴ったので取ると、取引は無いですが僕の知っている製造業の会社からでした。
しかも僕は先方の社長と面識があって直接の連絡先も知っています。
知っている会社なので無下に電話も切れず、かといってなんか歯切れの良くない感じの対応で、最終的には「いや、用があったら直接社長に連絡しますよ」と言って切りましたが、間の悪い変な雰囲気でした。笑
後から電話番号を調べると営業代行だったことがわかりました。
たぶんレアケースだとは思います。
2つめ。
FAXやメールのパターン。
これは厳密には営業代行が絡んでいるかはわかりません。
どちらかというとダイレクトメール的な行為についての話です。
封書にしろEメールにしろ、営業代行でダイレクトメールを採用する例もあるのではと推測するので書きます。
Twitter(X)で絡みのある会社からうちの会社あてに宣伝のFAXやメールが届いたことがありました。
経緯はわからないのですが、普段良い感じの投稿や、やり取りを見ていても、そこにスタンスのギャップや矛盾を感じてしまうと、ちょっと引いてしまいます。
3. 技術的な内容がマニアック
町工場の技術はマニアックな内容が多いです。
路地を一本違えると、もう勝手が違う世界なので、しっかり理解をしておかないと営業が難しいです。
また、問い合わせに早く回答するようなテンポの速い営業活動と相性がいいです。
なのでローラー作戦でアポ取りするような方法はあまり魅力的に感じません。
自社の例では、研究所や大学の先生と直接連絡を取り合って内容を詰めることで、早くて合理的な製造活動を達成しているので、現時点では自社の取り組みとは相性が良くなさそうと感じました。
自分はとにかく情報の齟齬を避けるように動いています。
営業代行と知っていれば、その体(てい)で対応ができますが、ステルスで連絡してこられると「ん?なんでお互い知っている仲やのにこんな形で連絡してくるんやろう?」となって混乱します。
お互い信頼をもって接しているはずやったのに、「営業をかけたくて近づいてきていたのかな」と思うとショックに感じちゃうと思います。
ステルスマーケティングの罪ってこういうことなのかなと思いました。
怖いところは「質の悪い営業代行をかけてしまうと、クライアントの与(あずか)り知らないところで会社の評判が落ちる可能性がある」というところです。
実際に上記2つの例とも、クライアントとなる会社には直接伝えていないので、営業をかけた先でどのようなことが起こっているかは認識されていないと思います。
メリットもあるかもしれませんが、デメリットも認識して活用するのがいいと思います。
まとめ
規模や余力にもよるところが大きいですが、打合せや仕様擦り合わせの多い仕事を通じて顧客満足度を上げたり、利益率を上げたりするのであれば、営業や営業事務という機能を置くことで達成しやすくなると思います。
情報の齟齬が減れば、加工不良が減らせるという側面もあります。
上記の物理的な制約の部分も加味して「静かな環境にいたり、手の汚れない仕事をしている人が営業機能を兼務する」みたいな運用もありかもしれません。
いかんせん余裕がない小企業や零細企業のことなので、コストに見合ってできるだけ成果を大きく上げられるような形で進めていきましょう。