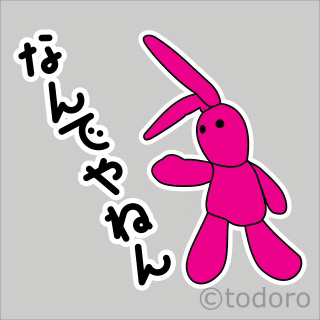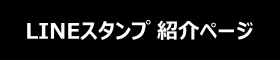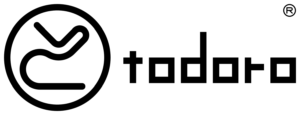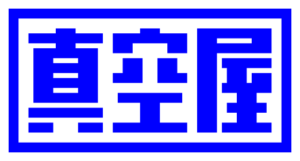学問のすすめ
福沢諭吉による最も有名な日本の書籍のひとつですね。
超が付くほどのベストセラーで、この書籍によって日本人がまるっと賢くなったと言われています。
ウィキペディアには「おそらく近代の啓発書で最も著名で、最も売れた書籍である。最終的には300万部以上売れたとされ、当時の日本の人口が3000万人程であったから実に全国民の10人に1人が買った計算になる。」と記載があります。
これは憶測ですが、当時の書籍は高級品だったでしょうから、買った本を1人で読んでしまい、とは考えづらいです。
共同購入も含め回し読みをしていたと考える方が自然で、そう考えると買ったのは1割でも読んだのは2割3割とも考えられます。
さらに子供なんか相手であれば、内容を口頭で伝えられたことも多かろうと考えると、ものすごい数になると思います。
「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という言葉が有名ですね。
引用をしたうえで「だからみんな本当は同じなんだ」「だから俺とお前は同じ生活をしないとおかしいんだ」「お前はずるいんだ」みたいな論調を見かけることがありますが、そうではないです。
そうではなくて、努力をして能力を向上させることに生まれ育ちは関係ない、天は人間に上も下も作らなかった、みんな平等に機会を与えられているんだ、ということが書かれています。
だから学問をすすめるんです。
そして学問というのは文字を読むことだけではないと明確に記載されています。
福沢諭吉という人は大変にユーモアもある人で、学問のすすめの中でそういう「文字を読み暗記するだけの人」を「文字の問屋」「飯を食う字引」という表現で痛烈に批判しています。
比喩がほんまにおもろいんですよね。笑
飯を食う字引はやばい。笑
読みながら声出して笑いました。笑
揶揄であり風刺ですよね。
ちなみに、生まれながらにして特権をもっている状態はおかしい、とも書かれています。笑
歌川国芳のようなロックを感じてしまう。笑
反骨精神による皮肉ってなんでこんなに気持ちいいんやろう。笑
そしてその内容は、今読み返しても筆に込めた想いが伝わってきて感動するほどの圧を感じます。
この国が大好きやったんやと思います。
歯がゆさを感じていたんやと思います。
まさに憂国。
叶わぬことですが、福沢諭吉と飲みに行ける機会があれば終始爆笑するやろなあと思います。
会社の方でも今年取引先になってくださったのですが、慶応義塾さん、さぞ良い学校なんやろうなあ。
結果的に「国力を上げた」と言われるほどの人で、だからこそ1万円の肖像に採用され、他の紙幣が刷新となる中、異例の二期続けての続投となったのでしょう。
十分に納得できることです。
新渡戸稲造もそのように言われたそうですが、海外との交渉時にも「あー、でも日本には福沢諭吉おるからなぁ」と大きな牽制力になったのではないでしょうか。
一個人が国力を上げるという嘘みたいな話です。
たまに学問のすすめを繙くことがあり、読むたびにやっぱりパンチ効いてるなと感じます笑。
初編と二篇だけでも、いつか子供たちも読んでほしい。
できれば歴史的仮名遣いで。
明治に出版された本なので歴史的仮名遣いでも比較的読みやすいです。
口を動かして読むと語調が本当に心地いいし筆に込めた想いに鳥肌が立ちます。
新幹線の中で読んで涙出てきて思わず焦るほど。笑
自分は仏教徒ではないながらも、般若心経(はんにゃしんぎょう)はおもろいなと思っていて考え方も好きなんですが、般若心経に絵心経(えしんぎょう)というものがあります、
「発音」を絵にして描いてあって、文字が読めなくても絵を口にしていくだけで読経をしたことになる、というものです。
日本では古来から言霊(ことだま)や言祝ぎ(ことほぎ)といって、口に出すことが力をもち、外に対して実際の影響を与えると言われています。
英語でもシャドーイングは英会話上達の近道といいますし、学ぶは真似ぶともいいます。
つまり「形から入る」ではないですが「形どってみる」みたいなことが学問にとても有効と僕は考えています。
形から入るとお金がかかることもありますが、形どってみるだけならお金がかからないことも多いですね。
この本、近年では読む人が少なくなっているかもしれません。
著作権も切れていて、青空文庫でタダで読めるので、まだの方はぜひ一度読んでみてはいかがでしょうか。